ご親族が亡くなられ、急遽、喪主を務めることになり、天台宗の葬儀の進め方がわからず、不安な気持ちでお過ごしのことと存じます。
慣れない儀式の連続に、「故人様のために、きちんと送り出してあげたい」というお気持ちと、「作法や流れを間違えたらどうしよう」という心配が入り混じっているのではないでしょうか。
大切な方とのお別れの時を、心穏やかに過ごすためにも、葬儀の全体像を把握しておくことは非常に重要です。
この記事では、天台宗の葬儀の基本的な流れから、焼香などの具体的な作法、さらにはよくある質問まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事を最後まで読めば、あなたが抱える不安は解消され、自信を持って故人様をお見送りできるようになるでしょう。
天台宗の葬儀とは?

天台宗の葬儀は、故人が仏の弟子となり、悟りの世界である仏の国(浄土)へ無事に旅立てるよう導くための、非常に大切な儀式です。
天台宗は平安時代に最澄が開いた歴史ある宗派で、その教えの中心には「法華経」があります。
この「法華経」の教えでは、生きとし生けるものは誰もが仏になる可能性を持っているとされています。
そのため、天台宗の葬儀は、故人がその可能性を開花させ、仏として生まれ変わるための重要なステップと位置づけられています。
具体的には、儀式を通じて故人の生前の罪や穢れを清め、仏の道を歩むための準備を整えるのです。
また、天台宗の大きな特徴として「顕教(けんぎょう)」と「密教(みっきょう)」という二つの教えが融合している点が挙げられます。
顕教は言葉で分かりやすく説かれる教え、密教は修行や儀式を重んじる秘教的な教えを指します。
葬儀ではこの両方の要素が取り入れられ、故人の成仏を力強く後押しする、荘厳で意味深いものとなっています。
 じぞ丸
じぞ丸天台宗の葬儀は、故人様が仏様になるための大切な儀式であり、顕教と密教の二つの教えが融合している点が特徴なのですね。
天台宗の葬儀の流れ


突然のことで戸惑われるかと存じますが、天台宗の葬儀の流れをあらかじめ知っておくことで、少しでも落ち着いて対応できるはずです。
ご臨終から火葬まで、葬儀はいくつかの段階に分かれています。
それぞれの段階でどのような儀式が行われるのか、喪主として何をすべきかを事前に把握しておきましょう。
ここでは、葬儀全体の流れを大きく3つのステップに分けて、具体的に解説していきます。
一つひとつの儀式の意味を理解しながら、故人様とのお別れの時間を大切に過ごせるように準備を進めましょう。
枕経から通夜までの段取り 天台宗の葬儀
ご臨終後、まず最初に行うべきことは、菩提寺(先祖代々のお墓があるお寺)への連絡です。
僧侶と相談し、枕経や通夜、葬儀の日程を決めていきます。
枕経とは、故人様の枕元でお経をあげていただく最初の儀式です。
本来は臨終の間際に行われていましたが、現在では病院で亡くなるケースが多いため、ご遺体を自宅や斎場に安置したあとに行うのが一般的です。
枕経は、故人が仏の弟子となるための大切な準備であり、残された遺族の心を落ち着かせる意味合いもあります。
ご遺体を安置したら、「枕飾り」と呼ばれる小さな祭壇を準備します。
これらは葬儀社が手配してくれることがほとんどですので、相談してみましょう。
その後、近親者で故人様を見守りながら過ごす「通夜」の儀式に移ります。
通夜では、僧侶による読経が行われ、故人が浄土へ無事に導かれることを祈ります。
天台宗の通夜では、阿弥陀如来のお迎えをいただくためのお経が唱えられることが多いです。
また、故人に戒名を授ける「授戒式(じゅかいしき)」や、髪を剃る(実際には剃る真似をする)「剃度式(ていどしき)」といった儀式が行われることもあります。
これらの儀式を経て、故人様は仏の弟子としての歩みを始めるのです。
葬儀本儀の進行 天台宗の葬儀
通夜の翌日には、葬儀・告別式が執り行われます。
葬儀は、故人を仏の世界へ送るための宗教的な儀式です。
天台宗の葬儀は、顕教と密教の要素が融合した荘厳な儀式が特徴です。
まず、導師(僧侶)が入場し、楽器が奏deられる中で儀式が始まります。
葬儀の前半では、「光明供修法(こうみょうくしゅほう)」など、密教の作法によって故人を清め、仏と一体化させるための儀式が行われます。
その後、「授戒式」で故人に仏弟子としての戒名を授けます。
これは、故人が仏の道を歩む上で守るべき教えを授かる、非常に重要な儀式です。
次に、「引導(いんどう)」という儀式が行われます。
これは、導師が故人の徳を讃え、迷わず浄土へ旅立てるように導くもので、松明や線香で空中に梵字を描くといった象徴的な作法がとられることもあります。
続いて、天台宗の教えの中心である「法華経」などが読経され、参列者は故人の冥福を祈ります。
読経が終わると、導師が退場し、葬儀の儀式は終了となります。
一連の儀式は、故人が仏の弟子となり、安らかに浄土へ向かうための大切な道のりなのです。
告別式の手続き 天台宗の葬儀
葬儀に引き続いて行われるのが告別式です。
葬儀が故人を仏の世界へ送る宗教的な儀式であるのに対し、告別式は、生前お世話になった方々が故人との最後のお別れをする社会的な儀式という側面があります。
現在では、葬儀と告別式を明確に区別せず、一連の流れとして行うことが一般的です。
告別式の主な内容は、弔辞の奉読、弔電の紹介、そして参列者による焼香です。
弔辞は、故人と親しかった友人や関係者がお別れの言葉を述べ、故人との思い出を偲びます。
その後、寄せられた弔電が読み上げられます。
そして、喪主、遺族、親族、一般参列者の順で焼香を行い、故人に最後の別れを告げます。
全員の焼香が終わると、喪主が参列者に対して挨拶を述べ、生前の感謝の気持ちを伝えます。
挨拶が終わると、棺に花などを手向ける「お花入れの儀」を行い、故人との最後の対面をします。
そして、棺の蓋を閉じ、霊柩車まで運び、火葬場へと出棺します。
この一連の流れを通じて、故人との思い出を胸に刻み、感謝の気持ちとともに送り出すのです。



ご臨終から出棺まで、故人様を送り出すために様々な儀式が行われるのですね。それぞれの意味を理解して、心を込めてお見送りすることが大切だと感じました。
天台宗葬儀の式次第の一例
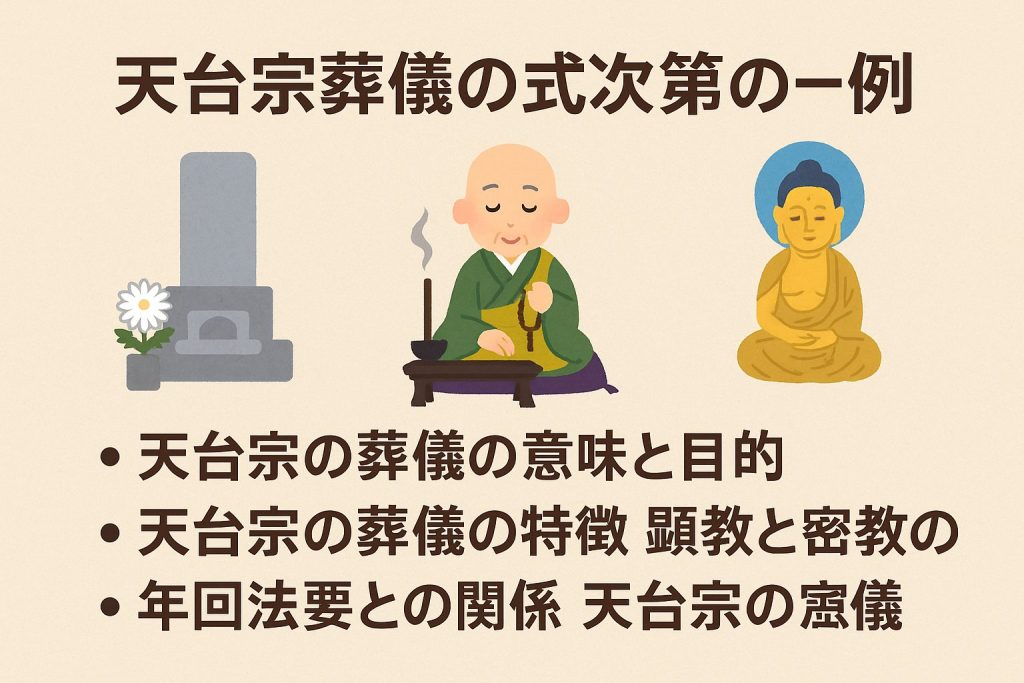
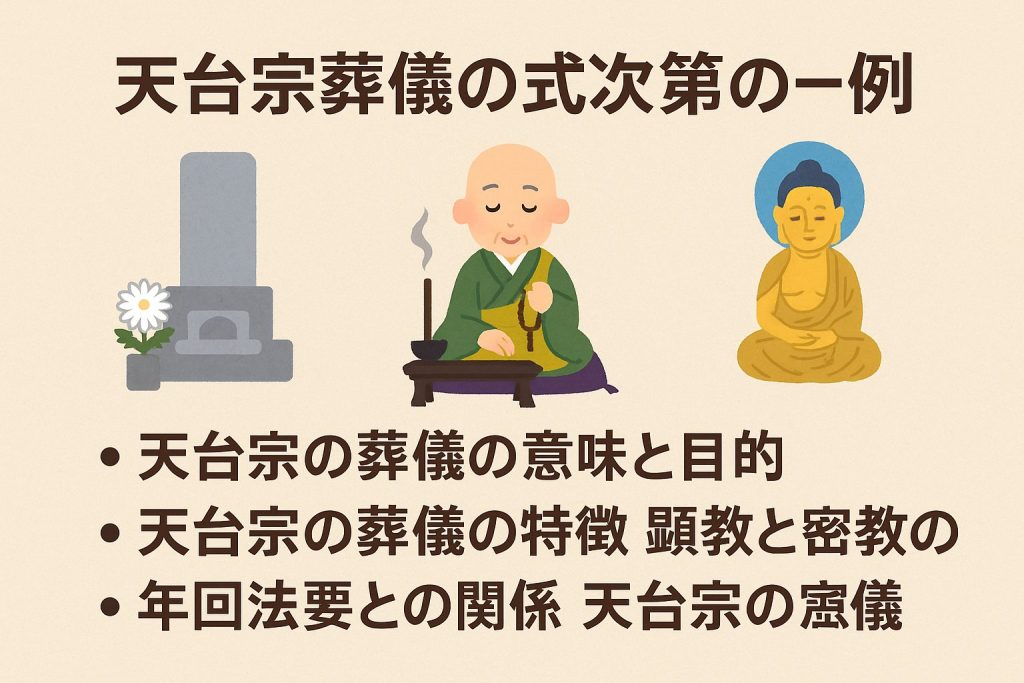
天台宗の葬儀は、故人が仏の弟子となり、安らかに浄土へ旅立つための儀式です。
その式次第には、一つひとつに深い意味が込められています。
天台宗ならではの特徴を理解することで、より一層心を込めて故人様をお見送りすることができるでしょう。
ここでは、葬儀が持つ本来の意味や目的、そして天台宗の最大の特徴である顕教と密教の観点から見た儀式の特色、さらには葬儀後の年回法要とのつながりについて解説します。
これらの知識は、喪主として儀式に臨む際の心の支えとなるはずです。
天台宗の葬儀の意味と目的
天台宗における葬儀の最も大切な目的は、故人の魂を安らかに仏の国(浄土)へ導き、成仏を遂げてもらうことです。
天台宗の教えの根幹には、「すべての人は仏になることができる」という法華経の考え方があります。
葬儀は、故人がその可能性を現実のものとするための、極めて重要な儀式と位置づけられています。
人はこの世で、意識せずとも多くの罪を背負ってしまうと考えられています。
そのため、葬儀ではまず、故人の身体と心を清める儀式が行われます。
水や香で身体を清め(洒水・塗香)、懺悔の言葉を唱えることで心を清浄にするのです。
そして、戒名を授かることで正式に仏の弟子となり、仏の教えを守ることを誓います。
このように、心身ともに仏の弟子となる準備を整えた上で、導師の導きによって浄土へと旅立っていくのです。
残された遺族にとっては、故人が迷うことなく、安らかな世界へ向かうことを祈る大切な時間となります。
葬儀を通じて、故人の冥福を祈り、感謝の気持ちとともに送り出すことが、最大の供養となるのです。
天台宗の葬儀の特徴 顕教と密教の観点
天台宗の葬儀が他の宗派と大きく異なる点は、「顕教(けんぎょう)」と「密教(みっきょう)」という二つの要素が融合していることです。
この「顕密融合(けんみつゆうごう)」こそが、天台宗の最大の特徴と言えるでしょう。
顕教とは、お経など言葉や文字を通して、誰にでも分かるように説かれた教えのことです。
葬儀においては、主に「法華経」などが読誦され、その教えの力によって故人の成仏を願います。
一方、密教とは、言葉だけでは伝えきれない深遠な教えであり、印を結んだり真言(仏の言葉)を唱えたりといった、儀式的な作法を重んじます。
天台宗の葬儀では、「光明真言(こうみょうしんごん)」を唱えたり、特別な印を結んだりする密教法要が行われます。
これにより、故人の生前の罪を滅し、災いから身を守り、力強く浄土へと導くと考えられています。
つまり、顕教の教えで理論的に故人の成仏を願い、密教の儀式の力でそれを強力に後押しするという、二つのアプローチが組み合わさっているのです。
この荘厳で奥深い儀式によって、故人は迷うことなく仏の世界へと旅立つことができるとされています。
年回法要との関係 天台宗の葬儀
葬儀は故人を送り出すための一つの区切りですが、供養はそれで終わりではありません。
葬儀後も、故人の冥福を祈り、故人を偲ぶための大切な儀式として「年回法要(ねんかいほうよう)」が続きます。
年回法要は、故人が浄土でより良い世界へ生まれ変わるための修行を後押しする「追善供養(ついぜんくよう)」の意味合いを持っています。
遺された家族が善い行いをし、その功徳を故人に振り向けることで、故人の浄土での暮らしがより安らかなものになると考えられているのです。
亡くなった日から数えて七日ごとに行う法要が四十九日まで続き、この期間を「中陰(ちゅういん)」と呼びます。
特に四十九日は「満中陰」と呼ばれ、故人の行き先が決まる重要な日とされ、忌明けの法要が営まれます。
その後は、百箇日、一周忌(亡くなってから満1年目)、三回忌(満2年目)と続きます。
天台宗では、その後、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十五回忌、三十三回忌と法要を営むのが一般的です。
これらの法要は、故人を供養するだけでなく、親族が集まり、故人の思い出を語り合い、命の尊さやご縁に感謝する大切な機会でもあるのです。



天台宗の葬儀は故人様の成仏を願う深い意味があり、葬儀後も年回法要を通じて供養を続けることが大切なのですね。
天台宗の葬儀の作法
葬儀に参列する際、特に気になるのが焼香や数珠の扱い方といった作法ではないでしょうか。
喪主として、また参列者として、正しい作法を知っておくことは、故人様への敬意を示す上で非常に大切です。
天台宗には独自の作法がありますが、基本的なポイントを押さえておけば、決して難しいものではありません。
ここでは、天台宗の葬儀における焼香の手順と回数、そして特徴的な数珠の持ち方について、分かりやすく解説します。
いざという時に慌てないよう、事前に確認しておきましょう。
天台宗の焼香の作法 回数と手順
焼香は、故人様への供養の気持ちを香りに託して仏様に捧げる、大切な作法です。
天台宗の焼香の作法は、以下の手順で行うのが基本となります。
まず、焼香台の一歩手前で遺族と祭壇(ご本尊・ご遺影)にそれぞれ一礼します。
焼香台の前に進み、右手の中指・人差し指・親指の三本で抹香(粉末状のお香)を少量つまみます。
そして、つまんだ抹香を目の高さまで持ち上げ、額に押しいただくようにします。
この動作は、故人への敬意と感謝の心を表すものです。
その後、静かに香炉の炭の上にくべます。
この一連の動作を何回行うかについては、天台宗では明確な決まりはありませんが、基本的には3回繰り返すとされています。
この3回という回数は、仏・法・僧の三宝に帰依するという意味が込められています。
ただし、参列者が多い場合など、状況によっては1回に短縮されることもあります。
司会者から案內があった場合は、その指示に従いましょう。
焼香が終わったら、再度、祭壇に向かって合掌・礼拝し、最後に遺族に一礼して席に戻ります。
心を込めて丁寧に行うことが何よりも大切です。
天台宗の数珠の扱い方
数珠は、仏様と心を通わせるための大切な法具です。
天台宗で正式に用いられる数珠は、「平玉(ひらだま)」と呼ばれる、薄い楕円形やそろばん玉のような形をした主玉が108個連なっているのが特徴です。
これは他の宗派には見られない独特の形状です。
合掌する際の持ち方は、まず数珠の輪を人差し指と中指の間にかけ、房が下に垂れるようにします。
そして、そのまま両手を合わせます。
移動する際や座っている時は、数珠を二重にして左手で持つのが基本的な作法です。
親玉から伸びる房が下に垂れるように持ちます。
ただし、ご自身の宗派の数珠(略式数珠など)を持参してもマナー違反にはなりません。
大切なのは、数珠を丁寧に扱い、故人や仏様への敬意を忘れないことです。
床に直接置いたり、ポケットに無造作に入れたりせず、大切に扱いましょう。
もし正式な数珠の持ち方に不安がある場合は、周りの方の所作を参考にするか、事前に葬儀社のスタッフに確認しておくと安心です。



焼香や数珠の扱い方には宗派ごとの作法がありますが、最も大切なのは故人様を敬う心なのですね。
天台宗の葬儀に関するよくある質問
葬儀を執り行うにあたっては、細かな疑問や不安が次々と出てくるものです。
特に、普段あまり馴染みのない宗教的な儀式については、分からないことが多くて当然です。
ここでは、喪主様が抱きがちな天台宗の葬儀に関するよくある質問をまとめました。
枕経や通夜の準備から、焼香の回数、数珠の種類、地域による違い、そして年回法要の時期まで、具体的な疑問に一つひとつお答えしていきます。
事前にこれらの知識を得ておくことで、当日の不安を少しでも和らげることができるでしょう。
枕経や通夜の準備は何が必要か
枕経や通夜を行うにあたり、まず必要なのは僧侶をお迎えする準備です。
ご遺体を安置したら、故人様の枕元に「枕飾り」と呼ばれる小さな祭壇を設けます。
これには、香炉、燭台、花立ての三具足や、一膳飯、水などを供えますが、通常は葬儀社が準備してくれますので心配はいりません。
ご自宅で行う場合は、僧侶に座っていただくための座布団を用意しましょう。
読経が終わった後に、お茶やお茶菓子をお出しすることも心遣いとなります。
また、枕経の後には、僧侶と通夜や葬儀の日程、戒名などについての打ち合わせを行うのが一般的です。
喪主や遺族の服装は、この時点ではまだ喪服でなくても構いませんが、黒や紺など地味な色の平服が望ましいでしょう。
参列する近親者も同様で、香典を持参する必要はありません。
香典は通夜や葬儀の際にお渡しするのがマナーです。
何よりも大切なのは、故人を偲び、静かに冥福を祈る心です。
わからないことがあれば、遠慮なく葬儀社のスタッフや菩提寺に相談しましょう。
天台宗の焼香の回数は何回か
天台宗の焼香の回数には、実は厳密な決まりがありません。
一般的には1回または3回行うことが多いとされています。
僧侶が葬儀中に行う場合は3回と定められていることが多いですが、一般の参列者の場合は、状況に応じて変わります。
3回行う場合、その回数は「仏・法・僧」の三宝に帰依することや、貪り・怒り・愚かさという三つの煩悩を清める、といった意味が込められています。
一方で、参列者が多い場合など、時間に限りがある際には、心を込めて1回だけ行うこともあります。
葬儀の司会者から「焼香は1回でお願いします」といった案内がある場合は、その指示に従うのがマナーです。
特に案内がない場合で迷った際には、前の人の作法に倣うか、心を込めて1回行うとよいでしょう。
回数そのものよりも、故人の冥福を祈る気持ちを込めて、丁寧に行うことが最も大切です。
天台宗ではどの数珠を使うか
天台宗の正式な数珠は、主玉が扁平な形をしている「平玉(ひらだま)」で、主玉の数は煩悩の数と同じ108個あるのが特徴です。
親玉から伸びる房には、さらに弟子玉と呼ばれる玉がついています。
この平玉の数珠は天台宗独自のものであり、熱心な檀家の方などが使用されます。
しかし、喪主やご遺族、参列者が必ずしもこの正式な数珠を用意しなければならないわけではありません。
どの宗派でも使える「略式数珠(片手数珠)」をお持ちであれば、それを使用しても全く問題ありません。
また、他の宗派に属している方が、ご自身の宗派の本式数珠を持参することもマナー違反にはなりません。
数珠は持ち主のお守りとしての意味合いもあるため、ご自身が持っているものを大切に使うことが推奨されます。
大切なのは、数珠を丁寧に扱い、故人や仏様への敬意を示す心です。
天台宗の葬儀の式次第は地域で違うか
はい、天台宗の葬儀の式次第や作法は、地域やお寺によって異なる場合があります。
天台宗は長い歴史を持つ宗派であり、全国各地に広がっていく過程で、それぞれの地域の慣習や文化と融合し、独自の発展を遂げてきました。
そのため、葬儀の基本的な教えや目的は同じですが、儀式の細かな流れ、読まれるお経の種類、焼香の回数といった具体的な作法に違いが見られることがあります。
例えば、焼香の回数が1回とされる地域もあれば、3回が基本とされる地域もあります。
また、葬儀の中で行われる儀式の内容も、菩提寺の考え方によって多少の違いが生じることがあります。
もし、ご自身の地域の作法や、菩提寺のやり方がわからない場合は、遠慮なく菩提寺の僧侶や、地域の事情に詳しい葬儀社のスタッフに尋ねることが最も確実です。
事前に確認しておくことで、当日安心して儀式に臨むことができます。
告別式と葬儀の違いは何か
「葬儀」と「告別式」は、現在では一連の流れとして行われることが多いため混同されがちですが、本来はそれぞれ異なる意味を持っています。
「葬儀」は、故人が安らかに浄土へ旅立てるように、僧侶が中心となって行う宗教的な儀式を指します。
読経や引導、授戒といった儀式はすべて葬儀に含まれます。
これは主に遺族や親族など、故人と近しい人々が、故人の成仏を祈るための時間です。
一方、「告別式」は、故人と生前に親交のあった友人や知人、会社関係者などが、社会的なお別れをするための儀式です。
弔辞の奉読や弔電の紹介、一般参列者の焼香などがこれにあたります。
かつては葬儀を終えた後、場所を移して告別式を行っていましたが、現在では葬儀式場などで葬儀に引き続いて告別式を行う形式が一般的になっています。
このように、葬儀と告別式は目的が異なりますが、どちらも故人を偲び、送り出すための大切な時間であることに変わりはありません。
年回法要の時期はいつか
年回法要は、故人の命日に行う追善供養の儀式です。
亡くなった年を1年目(一回忌)と数えるのが基本です。
まず、亡くなった日から数えて7日ごとに法要があり、7回目の四十九日で忌明けとなります。
亡くなってから満1年目の命日に行うのが「一周忌」です。
そして、満2年目の命日に行うのが「三回忌」です。
二周忌ではなく三回忌と呼ぶのは、亡くなった日(一回忌)を基準に数えるためです。
その後は、三と七のつく年に行われることが多く、七回忌(満6年目)、十三回忌(満12年目)、十七回忌(満16年目)と続きます。
天台宗では、二十三回忌と二十七回忌は省略し、二十五回忌(満24年目)を営むのが一般的です。
そして、三十三回忌(満32年目)をもって「弔い上げ」とし、個別の法要を終えることが多いです。
これらの法要は、命日当日に行うのが理想ですが、参列者の都合を考え、命日より前の土日などに行うのが一般的です。



葬儀に関する様々な疑問も、事前に知っておくことで不安が解消されますね。特に作法や時期については、菩提寺や葬儀社に確認することが大切だと分かりました。
まとめ 天台宗の葬儀の要点
この記事では、天台宗の葬儀について、その流れや作法、特徴などを詳しく解説してきました。
天台宗の葬儀は、故人が仏の弟子となり、安らかに浄土へ旅立つための重要な儀式です。
顕教と密教の教えが融合した荘厳な儀式を通じて、故人の成仏を願います。
急なことで不安も大きいかと存じますが、大切なのは故人を想う心です。
葬儀の流れや作法は、故人への感謝と敬意を表すためのものです。
もし分からないことや不安なことがあれば、遠慮なく菩提寺の僧侶や葬儀社のスタッフに相談してください。
彼らはきっとあなたの力になってくれるはずです。
この記事で得た知識が、あなたが少しでも心穏やかに、そして自信を持って故人様をお見送りするための一助となれば幸いです。
大切な方との最後のお別れの時間を、悔いのないように過ごされますことを心よりお祈り申し上げます。




コメント